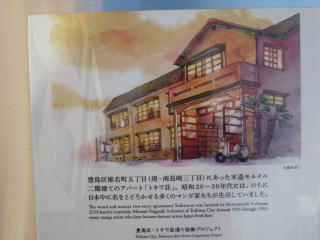この椎名町界隈は、もとは長崎村と呼ばれ、もともとは湿地帯で人が住めない場所であった。しかし、明治になると鉄道が敷かれ、池袋駅が誕生し、このあたりも発展し始めます。やがて池袋には立教大学が移転し、早稲田大学や学習院大学も近隣に創設され、その学生たちや関係者たちが落合村に住んでいたことから、近隣のこのあたりも大きな影響を受け、アトリエ付きの借家が立ち並ぶアトリエ村群ができていった。多くの芸術家たちが競い合い、励ましあったこの土地に、やがてトキワ荘に多くの漫画家たちが集まったのも偶然ではなさそうである。
1522年聖弁和尚(しょうべんわじょう)という僧侶によって開かれ、500年の歴史を誇る真言宗豊山派のお寺。歴代の住職から数えて33代目になる。17世紀後半には、幕府によりすでに古寺として認定されている。
江戸後期の天明年間、大火事の被災者を多く助けた功績として、将軍の縁戚にしか許されない朱塗りの山門建立を許可され、赤門寺とも呼ばれていた。一方で、地域の寺子屋として人々に親しまれ、この地の教育の原点でもあった。楽しイベントがたくさん行われ、「四国八十八箇所お砂踏み参拝所」や「長崎不動尊」など多くの信仰によって、季節折々に咲く花に囲まれた落ち着いた寺容を誇る名刹である。
~まんが地蔵~
創発としまの小林俊史氏監修のもと、トキワ荘協働プロジェクトメンバーの一乃瀬光太郎んと齊藤基貴さんがデザインしたもの。手塚治虫画ら著名な漫画家が居住していたトキワ荘の方角を見つめています。
光背がGペン先で、杖の代わりにペンが使われており、宝珠の代わりに「チエの実君」というキャラクターが使われています。創造の力を携わる縁結びのお地蔵さまということです。
昭和27年(1952)12月、豊島区椎名町5丁目(現・南長崎3丁目)に棟上げされた木造2階建てのアパート。老朽化により昭和57年(1982)11月29日に解体された。部屋のうち2階部分はすべて四畳半、共同の調理場、トイレなどが存在しました。現在は出版社が建っている。
手塚治虫は上京当時、新宿の八百屋の2階に下宿していたが、昼夜を問わぬ編集者の出入りの激しさについて八百屋の主人から苦情を言われるようになり、学童社の加藤謙一次男・加藤宏泰から、宏泰の住む新築アパート「トキワ荘」に入居するよう誘われ、1953年の初頭にここの住人となる。
以降、学童社が自社の雑誌で連載を持つ漫画家たちの多くをトキワ荘へ入居させ、最盛期には7~8名の漫画家たちが入居した。
その後入居した寺田ヒロオは、その後に入居してくる漫画家たちの兄貴分で、「空いた部屋には若い同志を入れ、ここを新人漫画家の共同生活の場にしていきたい」「新人漫画家同志で励まし合って切磋琢磨できる環境をつくりたい」との思いをもっており、その思いが漫画家たちを集めた要因の一つともなった。
 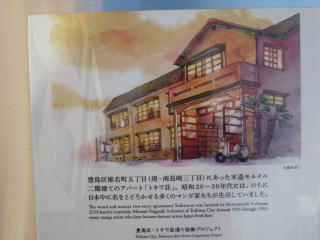
~トキワ荘ゆかりの地~
【松葉】多くの漫画に登場するラーメン店。トキワ荘に住んでいた漫画家たちもこのラーメン屋を愛していた。

【トキワ荘のヒーローたち】平成21年に建てられた記念碑。トキワ荘に住んでいた漫画家たちが掲載されている。

【子育地蔵尊】手塚治虫の「トキワ荘物語」にも登場。平成22年には建立300年を迎えた。

【落合電話局跡】トキワ荘の入り口正面にあった電話ボックス。昭和30年代の家庭には電話はほとんど普及しておらず、限られた出版社との通信手段でした。

【トキワ荘お休み処】平成25年に建てられた休憩・案内施設。1階はトキワ荘関連本や関連グッズが販売しており、2階は展示スペースとなっていて、寺田ヒロオの部屋を再現した展示となっています。
  
|